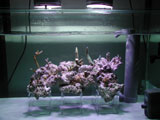HGSの立ち上げ
無生物相で立ち上げました。
それでは今回の立ち上げ方法をご紹介いたします。
用意するもの
1.ガラスOF(オーバーフロー)水槽 900×450×500
2.キャビネット
3.DR(デッドロック)
4.RO/DI水
5.人工海水(デルフィス)
6.クーラー ゼンスイCL500
7.ヒーター 500W
8.揚水ポンプ RSD40
9.プロテインスキマー H&S
10.DRリフトアップ用アクリル板
11.デジタル水温計
12.カルシウムリアクター(ぷ〜ちゃん作)
13.スーパークールブルー×2
14.CO2ボンベ
15.レギュレター
16.各種試薬
17.枝打ちミドリイシ
放流枝打ちミドリイシ(水が澄んだらアップします)
水質を測定してみました。
| |
|
RO/DI水 |
人工海水 |
飼育水 |
| アンモニア |
テトラ |
0 |
0 |
0 |
| 亜硝酸塩 |
テトラ |
0 |
0 |
0 |
| 硝酸塩 |
レッドシー |
0 |
0 |
0 |
| シリカ |
レッドシー |
0 |
わずかにブルー |
少しブルー |
| リン酸塩 |
レッドシー |
0 |
0.1ppm |
0.2ppm |
| KH |
テトラ |
|
|
8 |
| pH |
ピンポイント |
|
|
8.08 |
| 比重 |
シーテスト |
|
|
1.023 |
シリカ(珪酸)とリン酸塩は人工海水に少し含有しているようです。
この人工海水にシリカは飼育水の半分くらい(わずかです)リン酸塩
は0.1ppmほどの測定値でした。
DR(デッドロック)にも染みこんでいたのかもしれません。
PH(パワーヘッド)は今回使いません。
メインポンプのみの弱い水流で実験します。
2002年4月23日
3日後、かなり飼育水も澄んできましたがまだ少し濁っています。
リアクターに入れたメディアがアラゴナイトだったので・・・(-_-;)
それからPH(パワーヘッド)を使うことにしました。
ミドリイシを入れたときにミューカスが出たんだけど、これがサンゴやデッドロックに引っ掛かっていました。PHを付けたらかなりのミューカスのカスが舞いました。
揚水ポンプはRSD40を使いましたが、クーラーを通すとかなり水流が殺されてかなり弱い水流になってしまったので、とりあえずマキシジェット550と首振りPHの2台を追加する事にしました。それでも水流はかなり弱いです。
2002年4月24日
昨日取り付けた2個のPHを外し、RIO2500を1個にしてみました。
ちょっと強いかな?って思ったけどね。
するとデッドロックに乗せてあったミドリイシがコロコロと・・・
そしてデッドロックからはミューカスのカスがまだあったようで、水槽の中を舞っています。転げ落ちたミドリイシからまたミューカスが!(-_-;)
水流はかなり強くなりましたが砂がないのでメチャクチャ気持ちがいいです。水流はしばらくこのままで様子をみることにします。
ミドリイシは特に変化はありませんね。当たり前!(゜゜☆\(--メ)ポカッ
2002年4月25日
今日で5日目ですが、やっとアラゴナイトで濁っていた飼育水も澄んできました。
ここで放流したサンゴをご紹介いたします。
サンゴを放流してから4日目になりますが、やっといじけていたミドリイシ達もメイン水槽と同じような調子が出てきました。ヾ(*ΦωΦ)ノ ヒャッホゥ
これからどうなって行くのでしょうか?非常に楽しみですね。
添加剤を使用するか、微量元素の補給という意味での部分換水を頻繁にするか迷うところですがどうなんでしょう?
2002年4月26日
例のシリカ含有のためか、今日になって初めて茶苔(珪藻)がLR(ライブロック)や塩ビの底面に少しだけ付き始めました。良質なLRであれば珪藻は付かないと思います。
2002年4月27日
何も変化はありません。
一番左上のポリプを出さないタイプの枝ミドリイシは、照明が強い気がしたので手前の下の方に移動させました。
観察をしてみて感じることは、立ち上げ期間ってあるんだろうか?って気がしています。
ミドリイシが水質を汚すのであれば、そしてその汚れがスキマーで回収しきれないのであれば、どこかでアンモニア→亜硝酸塩→硝酸塩という硝化作用が起こるはずなんだけど、今のところこの3種類は試薬で測定しても0なんですよね。
今後もこのままの状態であれば、このシステムに立ち上げ期間は必要ないと言うか存在しない気がしていますがどうなんでしょう?
そもそもこのHGSystemで立ち上がったというのはどの時点を指すのかな?
これから硝化作用が始まるのでしょうか?
好気性バクテリアの餌があればそうなるはずですよね。
4月28日
スキマーの排水を見てみると色が付いていました。
匂いを嗅いでみると抹茶のかほりがしました。
4月29日
一昨日から飼育水がなんか濁っていました。夜寝る前に横から覗いて確認したんだけど、例のアラゴナイトの微粉がガラスに付いているのかもしれないと思っていました。昼間は気が付かなかったので、消灯後に濁ってくる気もしていましたが・・・
今日帰宅したのが遅かったので、照明を付けてみると・・・\(>o<)/ギャー!
珪藻が出てきました・・・それも一気にです!
一昨日から気になっていたことがもう一つありました。それは油膜が出始めたことです。OFパイプには油膜防止用に切り込みが入れてありますが、水流の関係か?上手く落ちていかないようです。(-_-;)
こうやって変化が現れてくると面白いですね。 ̄m ̄ ふふ
サンゴに異常は見られず、ちゃんとポリプを出していました。
5月3日
茶苔が一度どびゃ〜って出てから掃除をしてみたんだけど、それからはあまり出てこなくなりました。その代わりといっちゃ〜なんですが、ヒゲ苔みたいなものが生えだしてきました。(-_-;)
そこでヤドカリ1匹とシッタカ1匹を導入してみたんだけど、やっぱ効果がありましたわ!
しかし、シッタカのうんこちゃんは凄いね!メイン水槽はサンゴ砂が入っているからわからないけど、HGS水槽ではよ〜くわかりますだよ。
takaちゃん の日誌にも書いてあったので、興味のある方は見てみてみ!確か3月の日記に画像が載っていますよ〜。
の日誌にも書いてあったので、興味のある方は見てみてみ!確か3月の日記に画像が載っていますよ〜。
砂がないと掃除が超楽ちんどすよ! ̄m ̄ ふふ
サンゴは絶好調です。
これだけ調子が良いと逆につまんないな〜。
5月4日
シリカ(珪酸)も消費され尽くされただろうと思い、ついでにそれぞれの試薬で水質を測定してみることにしました。
| アンモニア |
テトラ |
0 |
| 亜硝酸塩 |
テトラ |
0 |
| 硝酸塩 |
レッドシー |
0 |
| シリカ |
レッドシー |
0 |
| リン酸塩 |
レッドシー |
0.2ppm |
| KH |
テトラ |
12 |
やっぱシリカはなくなったようですが、KNOPのリアクターに変更したためにKHが12にまで上昇してしまいました。バブルカウンターの泡が大きいからでしょう!
CO2を半分に絞って、1泡/2秒にしてみました。
リアクターの設定についてはそれぞれメーカーも違うので、全く同じような設定には出来ないはずですね。
何となく飼育水が濁っているので、活性炭をいれてみました。しかし、ビニール袋に入れて保存して置いたのですが、輪ゴムが劣化して切れて口が開いていました。(-_-;)
まぁ、入れてみることにしてみます。
5月5日
今朝起きて水槽を横から覗いてみると、驚くほど透明感がでていました。やっぱ活性炭の威力は凄いですね!この活性炭は工業用なのです。
もしかしてリン酸塩って活性炭で吸着させることが出来るのかな?って思い、リン酸塩を測定してみることにしました。
1.0ppmもあるど〜!\(>o<)/ギャー!
念のため全て測定してみたのですが、シリカが立ち上げ当初の淡いブルーになっていましたが、その他は0ppmでした。
活性炭が疑わしいですの!これから溶出したのであろうか?
もともと吸着されていたのか、口が開いていたので吸着したのかわかりませんが・・・
どうやら活性炭から溶出するようです。ココナッツカーボンが良いらしい・・・(-_-;)
早速ショップへ行ってフォスガードを買ってきました。
少しずつ使用して様子を見ることにしますが、全換水した方が早いかもしれません。
5月6日
さて、リン酸塩はまだ下がっていないと思うけど、とりあえず測定してみました。
1.0ppm まだあかんかったですわ〜。(゜゜☆\(--メ)アタリマエ!
ほんでリアクターのKHを下げるためにCO2を半分に絞ったんだけど、どうなっていたでしょうか?なんと15!もっとあかんがね!(-_-;)
こりゃおもっきし(*_*) マイッタ
よくよく考えてみると、リアクター内部には濃いKHの飼育水が入ってるのよね。
CO2は完全に止めてしまいました。徐々に下がってくるのを待つことにしますが、なんせミドリイシが少ないからどれくらいで下がってくるのかな?
ミドリイシは既に成長がみられるものもあります。
これからどうなっちゃうんだろう?このHGSystemは・・・
凄く楽しみです。
5月7日
気になっているリン酸塩濃度はどうなっているんでしょうか?早速測定してみることにしました。結果は・・・(‾ヘ‾;)ウーン1.0ppm〜0.5ppmの中間くらい?(o_□_)oドテッ
だってカラーチャートの色が微妙なんだも〜ん。
続きましてKHも測定してみました。結果は・・・13!
(´ρ`)ヘー KHってリアクターを止めるとこんなに早く下がっちゃうのかな?
でもそんなにミドリイシも入っていないんだけど・・・(-_-;)
測定ミスなのかな?もう一回計ってクルクル!
結果は・・・やっぱ13でしたわ。
それ以外はなんにも変化はごじゃりまへん。
5月9日
やっとリン酸塩が減ってきましたど!
今日測定したら0.2ppmまで下がっていました〜。
意外に早く吸着されたようです。
今回使用した活性炭は工業用のもので、仕事柄なんだけど仕入れ業者に頼んで入手したものです。エロエロ活性炭のことで質問したんだけど、アクア関係に使用するにはもったいないくらいの高価な活性炭だそうです。
ショップに売っているものは良くわからないけど、リンって溶出するのかな?
聞いたところによると、ココナッツカーボンはリンを溶出しないようなので、もし活性炭を使いたい時は、ココナッツカーボンを使用した方が安心なのかな?
ところで、活性炭を使用する前にリン酸塩を測定したところ、0.2ppmくらいの結果が出ました。念のためにRO/DI水を測定したところ、0だったのです。ほんでこのRO/DI水で溶かした人工海水を測定したところ、0.1ppmの値が出ました。と言うことは、残りの0.1ppmはどこから溶出してきたのか、調べたくなってきました。
考えられるのは、庭にほかってあったデッドロックか、リアクターに入れたアラゴナイトです。一度調べてみようと思っています。
とりあえずリアクターに入れたアラゴナイトを疑ってみました。
まずRO/DI水に人工海水を溶かし比重を1.023に合わせました。ここでリン酸塩の再確認をするために試薬で測定してみました。
RO/DI水=0ppm、RO/DI水で溶かした人工海水=0.1ppm
念のためにpH計を校正しました。
人工海水のpH=8.58
今まで作りたての人工海水のpHなんて測定したことがなかった気がするけど、意外に高い数値なんですね。ちょっとびっくらこきました。
次ぎにこの人工海水にCO2を適当にぶち込んでみました。
そして測定した結果pH=6.34ppmでした。
リアクターの排水程度を目標にしようと思ったんだけど、ちょっと低めなのかな?
まあ、アラゴナイトを溶かす為なのでこれくらいでいいでしょう。
ほんでシェイクシェイク!
さて、リン酸塩の測定をしてみましょう!
・・・・・\(>o<)/ギャー!
こんな真っ白な水なんて測定できんがね!(゜゜☆\(--メ)ポカッ
まいったまいったマイケルジャクソン!(*_*) ☆\(--メ)ポカッ
明日濾紙でも買ってくることにします。
5月10日
さてさて、今日は濾紙を買いに行ったんだけど売ってなかったんだよね。(T^T)
そこで昨日の白濁した水をどうしようかな?って考えていたんだけど、ええもんを
思いつきましたど。それはコーヒーで使う濾紙でまんがな!(^^)v
家について早速用意をしようとペットボトルを取りに行ったら・・・
w(゜o゜)wワオ!!透明になっていました〜 (o_□_)oドテッ
ではとりあえず注射器と試験管をこの海水で共洗いし、試験管に規定量入れました。
そして試薬で測定してみると・・・( ̄  ̄)………( ̄ー ̄)ニヤ
思った通りなのじゃ〜!
この画像ではわかりづらいと思うけど、リン酸塩濃度は0.1ppmでした。
やっぱARMを使わなければいけないのだろうか?
今度は普通のサンゴ砂とアラゴナイト、ARMの比較をしてみようと思います。
でも待てよ!確かにリアクターに詰めたアラゴナイトからリン酸が溶出している
んだけど、立ち上げて2日目に人工海水含有のリン酸0.1ppm+アラゴナイト
溶出0.1ppm=0.2ppmになるんだろうか?
やっぱデッドロックも同じように比較してみることにします。
5月12日
すんまそん・・・m(_ _"m)ペコリ
上のリン酸溶出テストの解釈なんですが、何かおかしくない?
だって、人工海水に0.1ppmリン酸が含有しているんだから、アラゴナイト
からは溶出していないってことになるじゃん!(o_□_)oドテッ
もしアラゴナイトから0.1ppmのリン酸が溶出しているのなら、0.2ppm
の結果になるよね!勘違いってやつです・・・(-_-;)
今日、普通のサンゴ砂とアラゴナイト、ARMのリン酸溶出テストの入ったんだ
けど、しょうもない結果になると思います。
ちゃんと分析に出した方がいいかもしれません。
やっぱりデッドロックから0.1ppmのリン酸が溶出したんでしょうね?
水質を測定してみました。
| アンモニア |
テトラ |
0 |
| 亜硝酸塩 |
テトラ |
0 |
| 硝酸塩 |
レッドシー |
0 |
| シリカ |
レッドシー |
0 |
| リン酸塩 |
レッドシー |
0.1ppm |
| KH |
テトラ |
11 |
リン酸は0.1ppmに下がりました。あれから1度リムーバーを取り替えて
まだ入っています。しばらく入れておこうと思ってね・・・
ほんでKHはやっと11dKHに下がってきました。
リアクターは止めたままです。
ミドリイシはかなり成長してきたものがあります。
 |
 |
| 2002年4月25日 |
2002年5月12日 |
 |
 |
| 2002年4月25日 |
2002年5月12日 |
特に枝打ちした部分の成長が著しいです。
ホソエダコモンの成長点が綺麗な紫色になってきました。
コーラルハクション( ̄ii ̄)のメインサンゴであるエダコモンはそれほど成長はしていないような気がするけど・・・
5月13日
リアクターメディアのリンについて調べて直してみました。
今回は普通のサンゴ砂、アラゴナイト、ARMの比較です。
昨日のことですが、前回のようにRO/DI水で人工海水を溶かし、CO2を適当にぶっこんでみたところ、偶然にも前回と同じ6.34のpHになりました。
ペットボトルに普通のサンゴ砂、アラゴナイト、ARMを入れ、pH6.34の人工海水を注ぎました。とりあえず1分間ほどシェイクして放置しておきました。
そして、朝起きてもう一回シェイクしておきました。
家に帰って試薬でリン酸を測定してみました。試薬はレッドシーです。
まずアラゴナイトを測定してみました。説明書通りにまずA液を8滴添加して試験管を振り、次ぎにB液を2滴添加して試験管を振ります。そして上から覗いて色をカラーチャートと比較するのですが、いつも通り30秒くらい発色するのを待ちました。結果は0.2ppmでした。ここでデジカメで発色を撮ろうと思い、カメラを取りに行ってきました。そしてもう一度発色を確認してみると、おやまぁ!なんと先ほどよりも濃い発色をしているではないか〜!(-_-;)
再度説明書を良く読んでみると、2分程待ってから発色を確認しろと書いてあります。
どうやら今まで発色しきる前に判断していたようです。念のためにもう一度時間と発色の変化を確認してみたところ、1分30秒くらいすると、それ以上の色の変化はないようです。5分経って同じ発色を示しているようですが、あまり長くそのままにしておくと、さらに変な色(濁った色)に発色するみたいです。結果は0.5ppmくらいでした!
今までリン酸をほとんど測定したことがなかったのですが、 ここで重大なことに気が付きました。レッドシーのリン酸試薬はちゃんと2分待ってから測定しましょう!
結果です、画像で比較してみましょう。
 |
 |
 |
 |
| 普通のサンゴ砂 |
アラゴナイト |
ARM |
HGS水槽 |
| 1.0ppm |
0.5ppm |
0.35ppm |
0.35ppm |
 |
 |
 |
 |
| メイン水槽 |
RO/DI水 |
水道水 |
RO/DI水+人工海水 |
| 0.2ppm |
0.1ppm |
0.1ppm |
0.2ppm |
試験管を直に置いたのでちょっと濃いめに写っています。
まぁ、皆さんそれぞれで考察して下さいね。
しかしRO/DI水が0.1ppm?本当かな・・・(-_-;)
シリカを測定してみると0ppmになっているので、ちゃんとRO/DIは機能していると思うんだけど、こんなもんなのかな?それとも試薬がおかしいのか??
BBSでお勧めの試薬を聞いて、再度比較してみたいと思います。
5月15日
リアクターを停止したのが5月6日だったけど、今日KHを測定したら9dKHに下がっていました。リアクターがないと下がるのは早いですね。
リアクター内部は循環していないので、念のためメディアを抜いて洗いましたが、海水は腐ってて硫化水素のかほりがしていました。(; ̄y ̄)c●〜〜クサイ、、、
KHの目標は8dKHです。とりあえずCO2はまだ添加せず、排水だけコックを全開にしておきました。いつでも再開できる用意だけで、これは特に意味はありません。
サンゴはいたって絶好調です。
5月20日
昨日メイン水槽を全換水したんだけど、人工海水が50Lほど余ってしまったので
HGS水槽の部分換水をしておきました。
(‾ヘ‾;)ウーン なんにもへんかありましぇん!(T^T)
5月25日
な〜んにも変化ごじゃりまへん。
5月27日
今日は久々に画像を載せようと思います。
| 2000年4月25日 |
2000年5月27日 |
2000年4月25日 |
2000年5月27日 |
 |
 |
 |
 |
| 2000年4月25日 |
2000年5月27日 |
2000年4月25日 |
2000年5月27日 |
 |
 |
 |
 |
まずは成長具合はこんなもんです。
なんか色が違ってきているみたいなんだけど、特に上段左のエダコモンを比較してみてね。サンゴの色もそうなんだけど、デッドロックの色も変わって見えますが、デジカメの設定はそのままだし画像の修正もないのに色が変わって見えるのは、スーパークールの色落ちなのでしょうか?
上段右はブルーが紫色になってしまっています。メイン水槽はブルーを維持しているので、光量の差なのでしょうか?
とにかくHGS水槽のミドリイシはポリプを良く出しているのですが、照明が消えた頃に出てくるポリプが昼間でも出ています。
このポリプは夜間に動物プランクトンを捕食するためのポリプだと思っていますが、メイン水槽の同じサンゴは点灯時はこのポリプは出ず、消灯時に出しています。
どうなんでしょうね?動物プランクトンを捕食したくてたまらず、こんなポリプを出しているようにも思えてしまいます。
ちなみに本日の画像は午後6時頃に撮影しました。
とにかくみんな良くポリプを出しています。
メイン水槽との最大の違いはこのポリプの出し方のような気がしています。
それから、デッドロックへの活着がすごい!
でもこれはたまたまなのかもしれません。
5月30日
今日はKHの試薬がなくなっていたので買ってきました。
早速測定してみたら、10dKHでした。
リアクターの設定は、CO2が1泡/5秒で排水が2滴/秒です。
メイン水槽の時はCO2が1.5〜2泡/1秒で排水は5ml/3秒でしたから、
全く設定が違いますね。それだけミドリイシが多いからなんでしょうか?
6月2日
今日はメイン水槽同様に部分換水を行いました。
総合添加剤は使用せず、定期的で徹底的な部分換水を行うことにしました。
ヨウ素とストロンチウムは添加しますが・・・
昨日はぷ〜ちゃん とデートしました。
とデートしました。
ほんで飼育水を少量渡してリン酸塩濃度を測定してもらいました。
HGS水槽はレッドシーで0.2ppmありますが、他の試薬ではどうなんでしょうか?
早速ご連絡をいただきました確かぷ〜ちゃんはサリファートだったっ毛?
0〜0.03ppmくらいだそうです!
(‾ヘ‾;)ウーン メーカーでこんなに違うもんなんかな?
いくらホビーといってもねぇ〜・・・(-_-;)
6月3日
リン酸塩試薬が届きました〜!
今回購入したのはサリファートですが、早速HGS水槽のリン酸濃度を
測定してみましたが、(‾ヘ‾;)ウーン やっぱカラーチャートが微妙で良く
わからないんだけど、0〜0.05ppmの範囲内だと思います。
こうなってくると何を信じて良いのかわからなくなってしまいます・・・(-_-;)
6月10日
HGS日誌も一週間サボってしまいました。(-_-;)
な〜んも変化ないのどすよ〜!(T^T)
しかし、ヒメマツミドリイシの成長が凄いんだじょ〜。
最近この水槽もつまらなくなって来ちゃいました。
なんか問題が出てくると燃えてく性格なので、こうもやることがないと
醤油入れたろか?とか
牛乳入れたらどうなるか?なんて思いませんが、なにかもの足らない
んだ著!(T^T)
もうこの辺で止めてもええどすか?(;´Д`A ```
6月12日
このHGSystemは、そもそも動物プランクトン及び生物相の多様化は必要か?
という疑問から立ち上げてみたのですが、今のところ必要ではないと言っても
OKだと思います。立ち上げから2カ月半が経ちましたが、まだ結論を出すのは
早いでしょうか?
ミドリイシが上手く飼えないってお悩みの方は、入門システムとしてこのHGSytem
に挑戦されてはどうなんかな?
難しいことは考える必要はありません。注意点は高KHの維持だけではないかと
思っています。カルシウムは全く考えていませんが、特に考えなくても自然とつい
てきてくれると思っています。
水流はそれほど強くなくても大丈夫だし、どうしてプランクトン云々言っているのか
理解できないですね・・・(-_-;)
あっ\(◎o◎)/!ミドリイシの付着物なのか、自然に発生してきたようなケヤリの
小さなヤツがデッドロックにくっついていましたよ。
生物相については逆にいえば、ミドリイシの付着物で十分なのでしょうか・・・
HGSの「動物プランクトンは必要か」に書きましたが、やはり以前教えていただいた通りで、閉鎖的環境下ではミドリイシに必要な微量の栄養塩があれば、動物プランクトンは必要ではないということの証明が出来たような気がしています。
もう少し続けてみて変化ないようであれば、この実験は終わりにしようと思います。
当然今の段階では生物相の多様化どころか、生物相を考えなくても良いのでしょうね。
メイン水槽をこのHGSytemにしようかと思ったんだけど、リセットも面倒クサクサだし・・・
このまま生物相の多様化は考えず、何も導入しないで続行していくことにします。
まぁ、今まで特に病気にもなっていないので大丈夫でしょう!(^^)v
| 2002年4月25日 |
2002年5月12日 |
2002年6月12日 |
 |
 |
 |
| 2002年4月25日 |
2002年5月12日 |
2002年6月12日 |
 |
 |
 |
ヒメマツミドリイシの成長は凄いです!
他はそれほどでもないんだけど、調子は良さそうです。
スキマーの汚水を見てみましょうか。
採取はこれで2回目です。
やっぱ緑色で抹茶のかほりで、思わず飲んでしまいました!(゜゜☆\(--メ)ウソコケ!
6月24日
こちらも久しぶりの更新ですな〜!(;´Д`A ```
ちょっと変化があったので、その内容を書こうと思いますだよ。
あれから無生物相の水槽も特に変化なく順調に成長しているので、そろそろこの実験は成功と言うことにして、メイン水槽のでかくなったサンゴをHGS水槽に4個ほど入れておくことにしました。黄色コモンは本当にでかくなって、LRにも覆ってしまっているので、LRごとの移動になりました。
移動して5日後に念のためKHを測定してみると、なんと6dKHに下がっていました!これだけのサンゴを追加しただけで、かなりのKHが消費されるようです。
CO2の量を増やしておきました。
それからもっと驚く現象がありました。
HGSのガラス面にはホンゲ〜沢山のプランクトンがはびこっています。でかいので全長1.5㎜くらいで、小さなものは肉眼はカタチがわからないほどです。多分この前移動したLRに付いていたものでしょうね。
でもメイン水槽にはそんなもん見たこともありませんのどすよ。なんでかな?
でも見えないだけで、実は動物プランクトンはちゃんといたんですね。
ちょっとビックリしました〜。
今までHGS水槽はこの動物プランクトンが入り込まないように注意してきたんだけど、これで完全にHGS水槽の実験は終わりを迎えることになりました。
10月6日
もう3カ月以上も経ってしまいました。
HGS水槽もメイン水槽と同じで、蒸発分の水分補給以外何もしていません。
現在の水槽です。
こちらも成長し続けていて、白化したミドリイシはありません。
照明の違いで、どうやら全体的に褐色に変わってきたような気がします。
シッタカの赤ちゃんが産まれました。超かわいいです・・・ ̄m ̄ ふふ
2003年2月16日
ほったらかしにしていたHGS日誌ですが、今年の1月に本格的に
メイン水槽をこのHGSにリセットしました。
このコーナーはこれにて終了ですが、引き続きホゲホゲダイアリー
で経過を報告しますね。
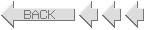
の日誌にも書いてあったので、興味のある方は見てみてみ!確か3月の日記に画像が載っていますよ〜。
とデートしました。